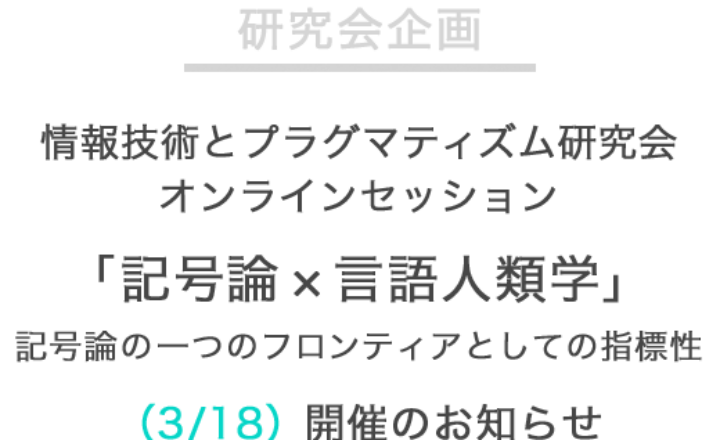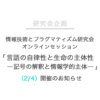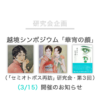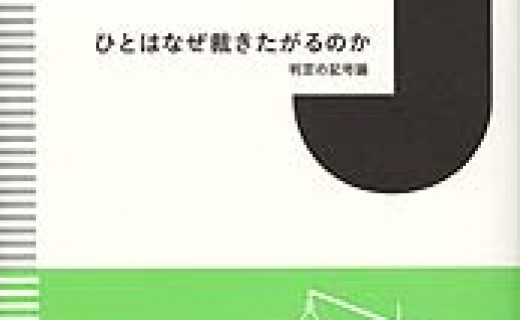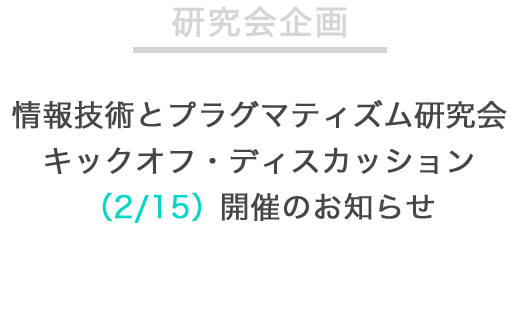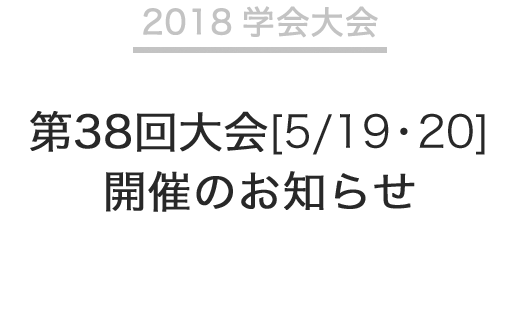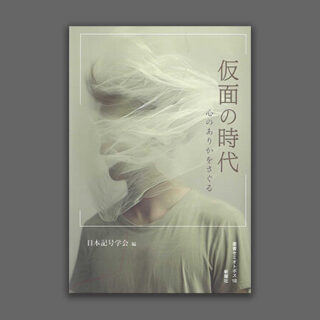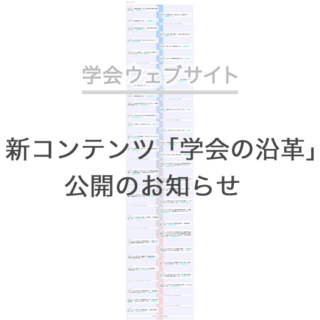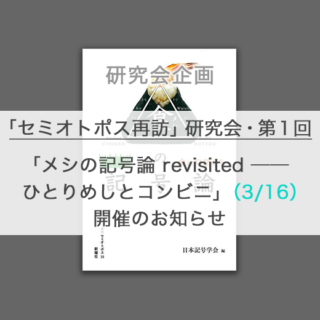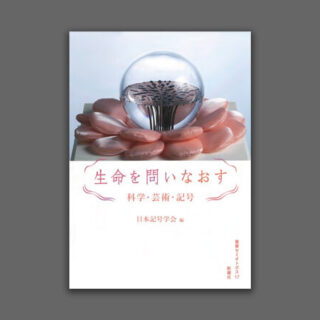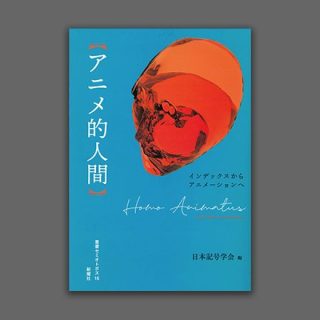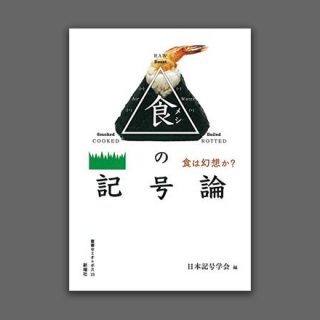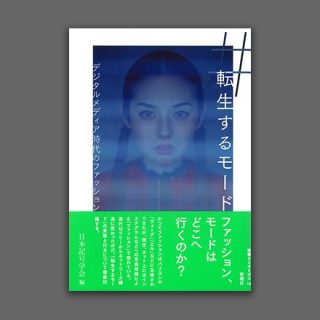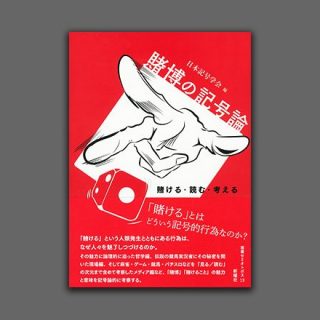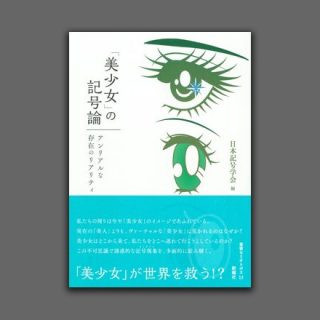「情報技術とプラグマティズム」研究会・オンラインセッション
「記号論×言語人類学:記号論の一つのフロンティアとしての指標性」
日時:2025年3月18日(火) 19:00 – 20:30[予定・若干延長有]
開催形態:オンラインセッション(Zoom予定)
参加方法:(⇒文末)
指標(インデックス)という記号はしばしば、写真が生み出す現実効果と結びつけられてきました。その根拠となってきたのは、光の痕跡を化学的に定着させるという写真の技術的な過程です。物理的な連続性によって現実の何かが確かに指し示されている、という指示作用の強度を掴まえることができる概念として、記号の指標性は有効であるとされてきました。しかしイメージがデジタルに生成される状況が一般化していくと、写真イメージにおける物理的な連続性は断ち切られることになります。必然的に、写真の指標性も根拠を失っていくことになりました。(☞ 情報技術とプラグマティズム研究会・セッション「貨幣としてのイメージ/資本としてのイメージ:もう一つの写真記号論に向けて」)
ところで、指標性に着目した表象分析を提起したロザリンド・クラウスの「指標論ノート」(1977)とほぼ同時期に、言語人類学者のマイケル・シルヴァスティンが「転換子、言語範疇、そして文化記述」(1976)という論文の中で、コミュニケーションの出来事性に光を当てる概念として指標性を取り上げました。発話内容が指し示す対象ではなく、社会的、文化的な文脈の中に発話行為自体が投錨されるという出来事性を指標の概念を通して捉えようとしたシルヴァスティンの構想は、特に言語人類学や社会言語学の領域で、社会的な指標性をめぐる議論の大きな流れを生み出していきました。
パースの記号論を下敷きとして展開されてきた言語人類学における指標性をめぐる議論は、しかし日本の記号論の文脈で十分に検討されてきたとは言えません。小山亘らによる訳業(『記号の思想 現代言語人類学の一軌跡:シルヴァスティン論文集』三元社、2009年)や解説書(『記号の系譜: 社会記号論系言語人類学の射程』三元社、2008年)はありますが、その根本にある指標性を軸とした記号をめぐる思想を、(少なくとも日本記号学会の文脈で)記号論の展開として受け止める、という作業はまだ行われてはいないのが実情です。
そこで本セッションでは、言語人類学を専門とする北海道大学の野澤俊介さんを報告者として迎え、記号論の一つのフロンティアとしての指標性をめぐって討議します。野澤さんのご報告では、言語人類学における指標性をめぐる議論を下敷きとした上で、とくにメディアやマテリアルな次元との接点に着目した最前線の理論的なフレームワークが提起される予定です。パースの指標の概念に立脚する言語人類学のフロンティアは、記号論にとっても同様にフロンティアであるはずです。そのフロンティアから見える光景を共有することで、日本の記号論がさらに先に進んでいくための手掛かりを得られるようなセッションにしたいと考えています。
テーマに関心を持っていただける幅広いオーディエンスのご参加をお待ちしています。
【タイムテーブル】
19:10 – 19:50 野澤俊介氏報告
報告タイトル「チャンネルのメタプラグマティクス:指標性の一つの変奏」
言語人類学(または「社会記号論系言語人類学」小山2008)ではパースの記号論とヤコブソンの動的な構造機能的視点との交差点を軸に、象徴記号体系としての言語をデフォルトのモデルとした(ソシュールのカルク的)思考の慣習の限界を示しつつ、コミュニケーションの出来事を形成する・に投錨される多様な記号過程に目を向けてきた。とくに記号過程における指標性(つまりプラグマティックな関係性)とそういった指標性を統制・変調・再生産する記号過程、つまりメタプラグマティクスの間の関係性に着目し、その諸条件と帰結について膨大な民族誌的知見の積み重ねがなされてきた。
本発表では、このようなこれまでの言語人類学的分析の一つのマイナーな変奏として、コミュニケーションの出来事における「チャンネル」に関わる記号過程をとりあげたい。ここでいうチャンネルとは、単純に、複数の場所や人、集団や物質をつないだり切断したりすることをいう。また、出来事の開始や監視、すれ違いや共鳴、摩擦や整頓、移動や占拠といった、チャンネルの上・中・外で巻き起こる様々な参与体の様相と参与枠組を指標(前提・創出)する記号過程を、ヤコブソンに依拠して、「交感」(phatic)的指標とよぶ。本発表では、ここ十数年ほどの間に発表されたチャンネル・交感の民族誌的再考の主だった具体例を紹介しながら、その今日的意義を考察したい。特にプラットフォームやインフラストラクチャ、メディアの物質性や流通をめぐる近年の領域横断的研究に(もとより領域横断的、全体の学である)言語人類学・社会記号論的視点を接続し分析することを可能とするメタ言語を共有することを、この発表の一応の理論的目論見とする。チャンネルや交感を(包摂的な概念というよりも)利便性のある合言葉またはショートカットとして考えるならば、この比較的シンプルでマイナーな概念の指し示す先に多様なスケールや形態の事象ーー海底ケーブル、アイコンタクト、霊媒、ネポティズム。。。ーーが立ち現れてくるだろう。
19:50 – 20:00 論点提起(谷島)
20:00 – 20:30 ディスカッション
報告者:野澤俊介(北海道大学)
司会:佐古仁志(東京交通短期大学)
論点提起:谷島貫太(二松学舎大学)
https://forms.gle/Aa34R4JieeXikxsW8
日本記号学会:情報技術とプラグマティズム研究会
(共同幹事:加藤隆文・谷島貫太・椋本輔)