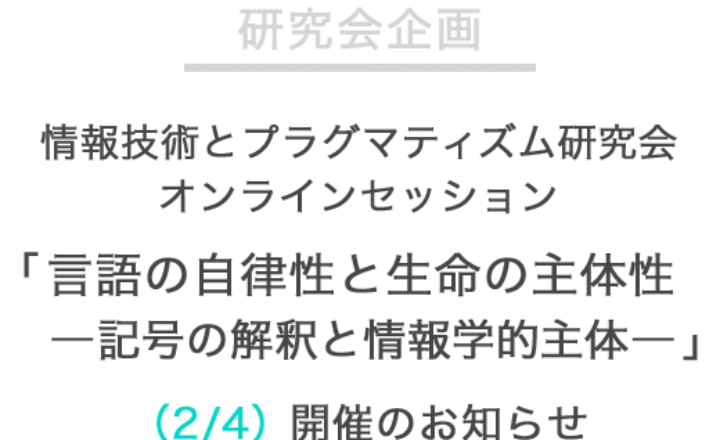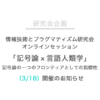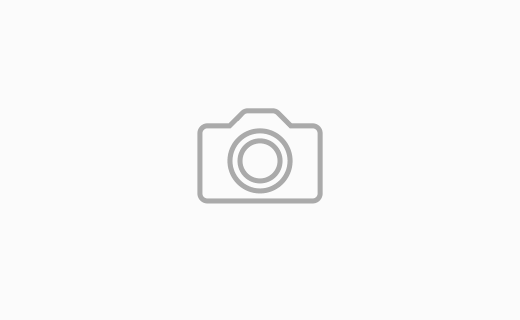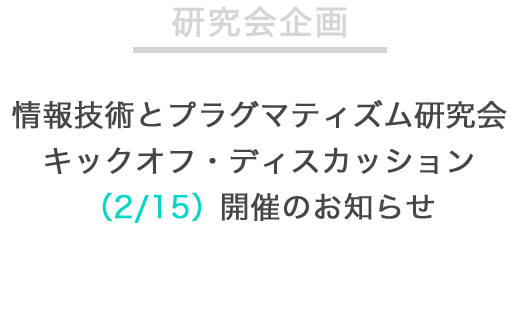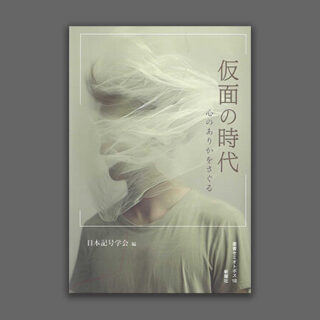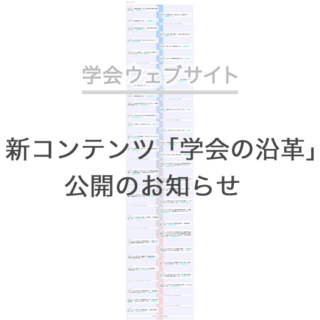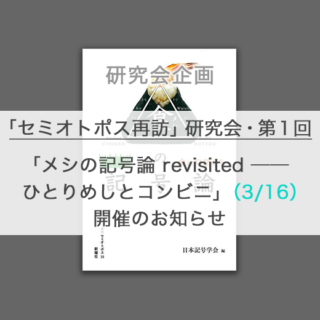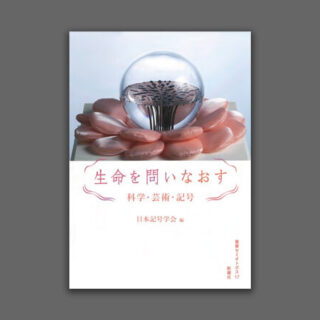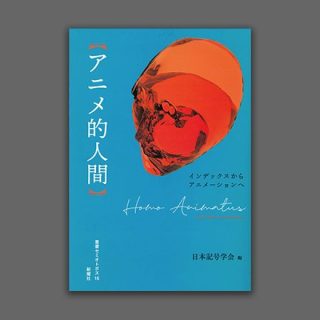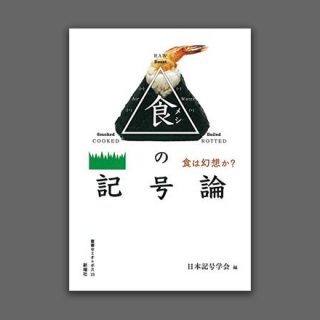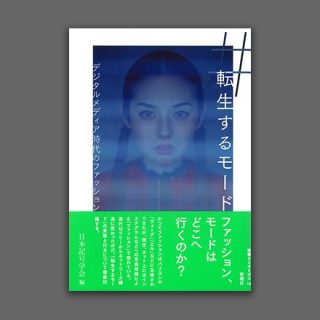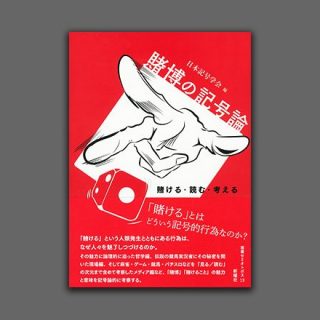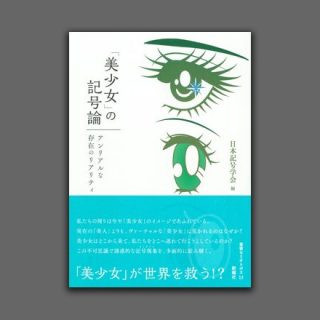「情報技術とプラグマティズム」研究会・オンラインセッション
「言語の自律性と生命の主体性―記号の解釈と情報学的主体―」
日時:2025年2月4日(火) 19:00 – 20:30[予定・若干延長有]
開催形態:オンラインセッション(Zoom予定)
参加方法:(⇒文末)
記号は、解釈によって意味をもつ。それは、パース記号論において文字通り「解釈項」を含む三項関係の記号過程というモデルで意識化されている。また、「意味するもの」と「意味されるもの」の恣意的な二項関係というソシュール記号学のモデルでも、非明示的であれ前提されている。では、その解釈はどのような主体によってなされているのか。また、なされ得るのか。この問いは従来も、生命記号論などのように、記号という概念の射程をより広汎に、より根源的なものとして考えようとするほどに(☞『記号論の逆襲』日本記号学会/2002)、それと対になる問題として存在してきた。
しかし、また新たな状況として今日、生成AIの急速な社会的一般化がある。特にその中心をなす大規模言語モデルに基づくAIシステムは、従来とは一線を画した、あたかも「人間のように言語を操る」主体として、我々の前に現れつつある。それは、従来のような個々のAIシステム単位での擬人化の問題とは異なる様相をもつ。我々人間の集合的な言語行為によって生み出された語と語の相互関係を、コンピューターで計算可能なデータの巨大な集合体として写し取った大規模言語モデルこそが、従来よりも格段に自律的なAIシステムの振る舞いを実現している。そうした大規模言語モデルにおける自律性と、我々人間の言語コミュニケーションにおける自律性とはどのような関係にあるのか。そして、言語生成AIに我々が感じる主体性とは何なのか、我々人間の主体性とそれは異なるのか、異なるとすればどう異なるのか。
このような主体性をめぐる現在的問題を、記号の解釈という観点から改めて考えてみたい。それはまた、昨年来の「情報技術とプラグマティズム」研究会での議論と密接な関わりをもつ、記号創発システム論における「記号はどのように創発するのか」という問いとも表裏の関係にある。(☞ 叢書セミオトポス18『仮面の時代:心のありかをさぐる』>第4部「ロボティクスと心――情報技術・システム論からのアプローチ」/2024)
そのために今回は、記号の解釈について「記号論的主体」「情報学的主体」という概念を提唱している、西田洋平さんをゲストに迎える。西田さんは、ネオ・サイバネティクス/基礎情報学の研究者として『人間非機械論:サイバネティクスが開く未来』(講談社選書メチエ,2023)等で知られる一方、生命記号論をはじめとした汎記号論における記号の解釈、解釈主体の問題についての論考もある。記号論における議論を、意味の観察主体を意識化するオートポイエーシス・システム論の観点から捉え直す、学際的な考察について発表頂く。
西田さんの発表を受けて、昨年2月のキックオフ・ディスカッション「情報技術×記号×人類学」でも登壇頂いた、会員の佐古仁志さんから応答を頂く。佐古さんは、パース記号論に造詣が深いとともに、基礎情報学やアフォーダンス等における議論も踏まえた「生態記号論」という観点を提唱している。西田さんからの発表に対して、主に自律性と主体性をめぐる論点を提起して頂き、セッション参加者とともに幅広く議論を展開していく。
【タイムテーブル】
19:00 – 19:10 導入(椋本輔)
19:10 – 19:40 発表(西田洋平)
19:40 – 19:55 応答(佐古仁志)
20:00 – 20:30 ディスカッション
発表者:西田洋平(東海大学)
応答・論点提起:佐古仁志(東京交通短期大学)
導入・司会:椋本輔(デザイン事務所代表)
https://forms.gle/fNcXc2Rip3ugVpVs7
日本記号学会:情報技術とプラグマティズム研究会
(共同幹事:加藤隆文・谷島貫太・椋本輔)