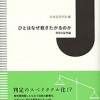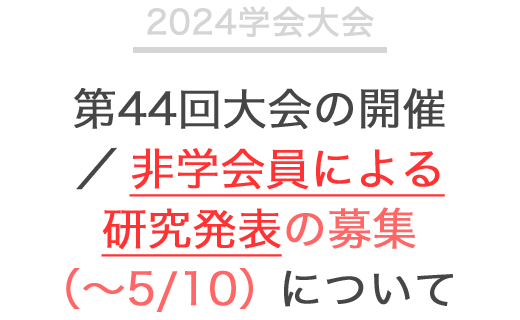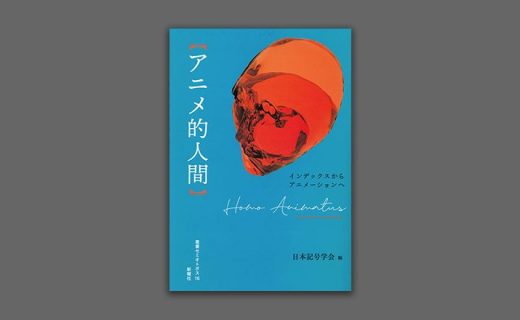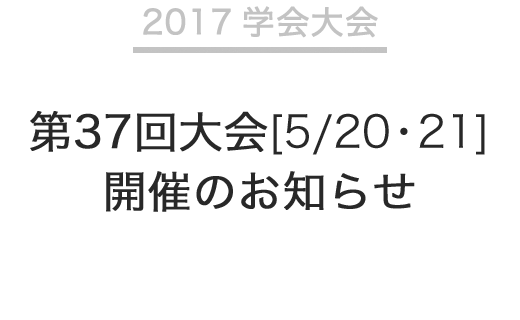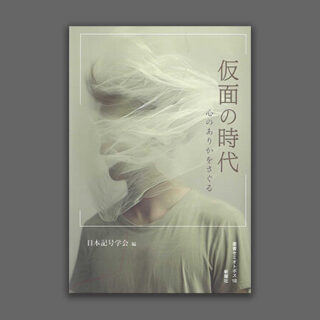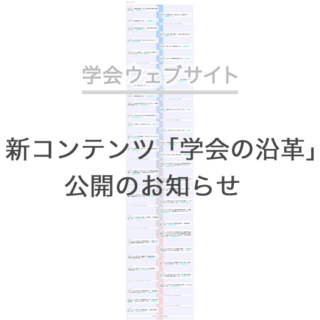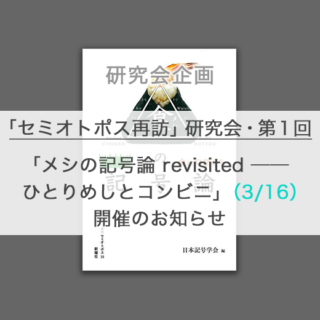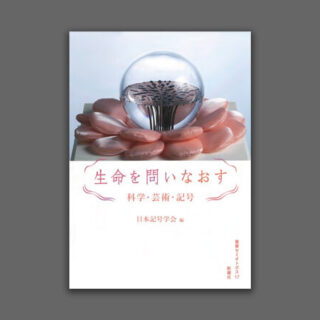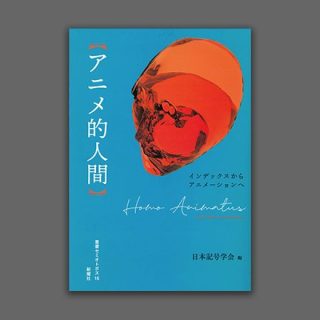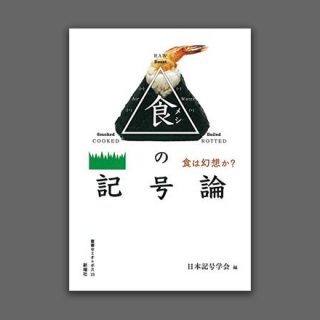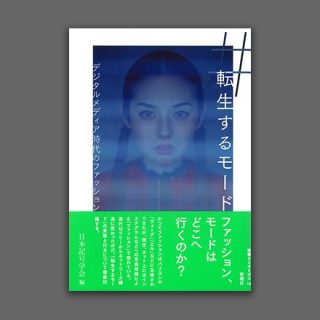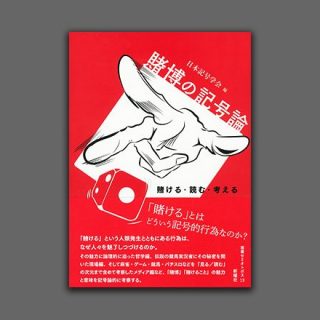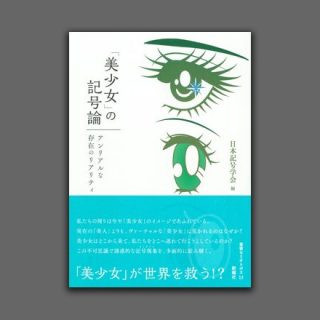FACEBOOKイベントページはこちら
大会プログラム(3.5MB)ダウンロード
日本記号学会第33回大会のお知らせ
第33回大会実行委員長 佐藤守弘
2013 年5 月18 日(土)、19 日(日)と、京都精華大学において日本記号学会第33 回大会を開催します。本学で行うのは、2004 年の第24 回大会「ケータイの記号論」に継いで2回目のことになります。
今回のテーマは、「〈音楽〉が終わったら――ポスト音楽時代の産業/テクノロジー/言説 When MUSIC is Over: Industry, Technology and Discourse in the Era of Post-Music」です。お気づきの方も少なくないと思いますが、この題はアメリカのロック・バンド、ザ・ドアーズの2 枚目のアルバム『まぼろしの世界』(Strange Days, 1967)の最後に収められた「音楽が終わったら」(Whenthe Music’ s Over)という曲のタイトルをもじったものです。ただ、元の曲が「the Music」と、ある特定の1 曲を指しているのに対して、「MUSIC」と定冠詞を外して音楽全般のことを指すように改変しました。
日常生活のあらゆる場所へデジタル技術が浸透した現在、今日の「音楽」を巡る状況はドラスティックに変化を遂げていると思います。インターネットを通じた音楽配信の問題や「初音ミク」などヴォーカロイドの登場については、さまざまなメディアや研究領域にて論議されています。もちろん、こうした状況の根源は19世紀末の録音という音の複製技術の登場から始まっているとも考えられます。あるいはテルミンやモーグによる物理的な発音源を持たない音響合成技術の開発や、コンピュータによる自動演奏技術が果たした役割も無視できません。
このような技術面での変化により、たとえばある勤め人が自宅で録音した音楽をインターネットにアップしたところ、イギリスの著名なDJ の耳に留まり、レコード/ CD /ネット配信で発売され、ラジオやクラブなどで掛けられるというような状況が生まれることとなります(これは私の友人の話です)。こうした変化は、作り出される音だけにとどまらず、音楽を巡る産業や言説にも影響を与えているようにも思えます。
従来の「音楽/ MUSIC」という枠組みでは捉えきれないような現代の状況――これは私の専門分野である視覚文化においても起こっています――を、門外漢の強みで「ポスト音楽」と勝手に名付けてみました。「音楽」自体は終わっていないかもしれません。でも、もし「音楽」が終わったとしたら、どういうことになるだろうか。こうした音楽以降の状況について私自身も知ってみたいという考えから、今大会のテーマを企画しました。
音楽を巡る状況の変化は、音/音楽のコミュニケーションのあり方自体への問い直しも要請するでしょう。こうした状況に記号学/記号論はどのように寄与するのか、会員の皆さんも交えた活発な議論を期待しています。
日本記号学会第33 回大会
「〈音楽〉が終わったら――
ポスト音楽時代の産業/テクノロジー/言説」
開催日:2013 年5 月18 日(土)・19 日(日)
会場:京都精華大学 黎明館
1 日目:5 月18 日(土)
セッション1+パフォーマンス「音=人間=機械のインタラクション」 黎明館L-101
The SINE WAVE ORCHESTRA[城一裕(情報科学芸術大学院大学[IAMAS]・音響学/インタラクション・デザイン)、石田大祐(アーティスト)]、RAKASU PROJECT.[落晃子(京都精華大学・電子音響)]、フォルマント兄弟[三輪眞弘(情報科学芸術大学院大学・作曲/メディアアート)、佐近田展康(名古屋学芸大学・メディアアート/メディア論)]、司会:吉岡洋(京都大学・美学/メディア理論)
2 日目:5 月19 日(日)
セッション2「音楽・産業・テクノロジー――音楽制作の現状」 黎明館L-101
佐久間正英(京都精華大学・音楽制作)、榎本幹朗(音楽コンサルタント)、山路敦司(大阪電気通信大学・作曲)、司会:水島久光(東海大学・メディア論)
セッション3「モノと人と音楽と社会――ポピュラー音楽研究のフロント」 黎明館L-101
南田勝也(武蔵大学・音楽社会学/情報メディア論)、土橋臣吾(法政大学・社会学/メディア研究)、谷口文和(京都精華大学・音楽学)、司会:安田昌弘(京都精華大学・文化社会学/ポピュラー音楽研究)