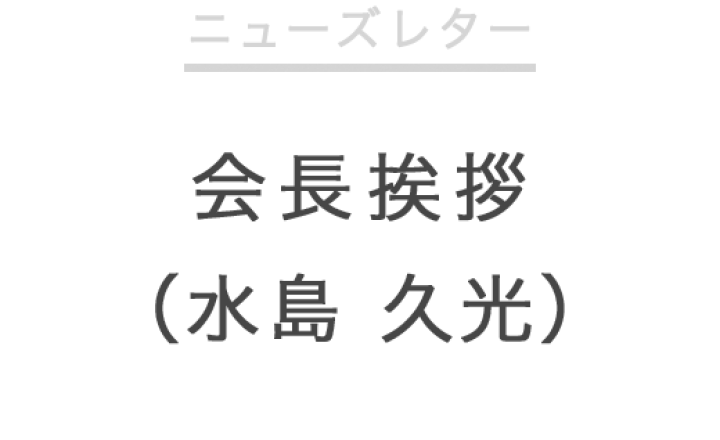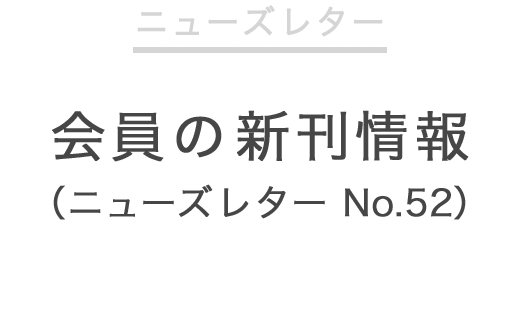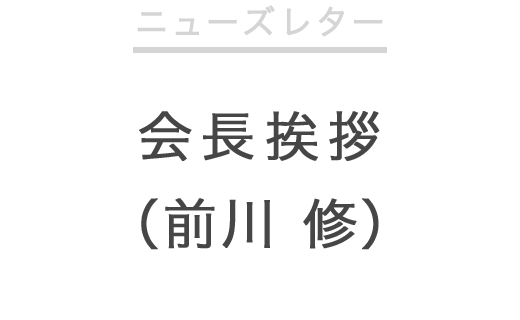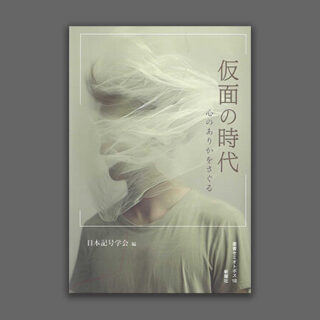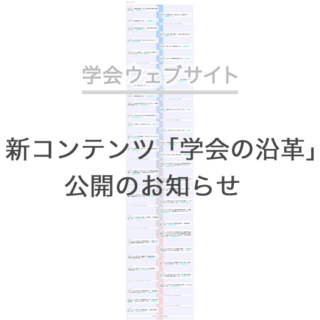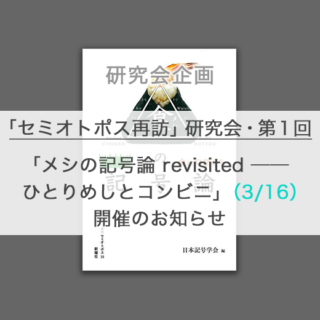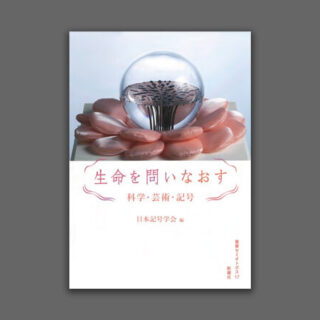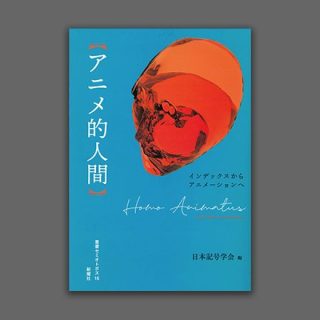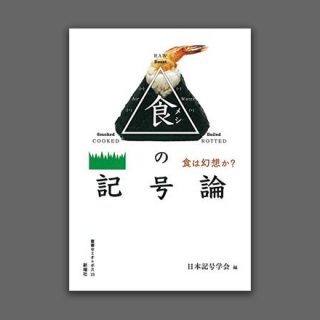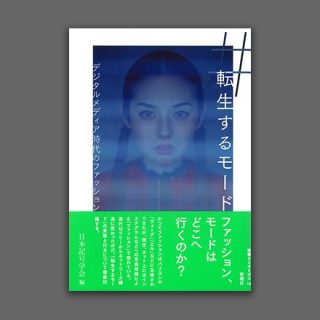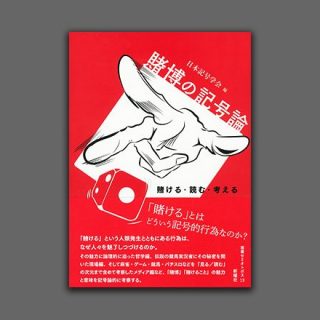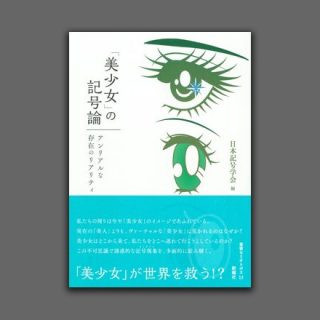みなさま、明けましておめでとうございます。それぞれ良い年をお迎えになられたことと存じます。日本記号学会のニューズレターでのご挨拶はおよそ半年ぶりになります。この間何度か、メールなどを通じて学会の動きなどのご案内を申し上げてまいりましたが、ようやく地に足をつけて運営をしていける体制が整いつつあります。
まずは、9月17日18日の二日間、松谷容作実行委員長の八面六臂の活躍に支えられ、第42回大会が無事開催できましたことをご報告いたします。今回は、会員相互の交流を図る目的のもと、追手門学院大学にて全プログラムを対面で実施しました。全報告・発表者の資料が掲載された特設サイトは引き続き公開していますので、ご参照ください。
また、同日開催された総会においては、会則の改訂をはじめとした重要案件がいくつか審議されました。改訂の内容については、本ニューズレターの総会報告で要点をご説明申し上げますほかに、新旧対照表を別紙にて同封いたしました。今後の学会運営に関してご理解を賜りたい点がございます。ぜひご確認いただきたく存じます。
重要案件の中で、特にここでお知らせしておきたいことは、電子ジャーナルの創刊についてです。詳しくはこれも編集委員会から説明がありますが、本ニューズレターをもって募集を開始し、11月の発行を目指すこととなりました。これには大きく二つの狙いがあります。それは学会の年間計画の正規化と、学会が目指す研究活動の明確化です。
これまで本学会への投稿論文は査読の上、学会誌『叢書セミオトポス』への掲載によって公開させていただいていました。しかしご承知のように近年学会誌の発行インターバルが不安定化し、掲載時期が確定できず、大変なご迷惑をおかけしてきました。今回よりメイン媒体を電子ジャーナルとすることで、まずこのようなことはなくなります。
新しいジャーナル名は『記号学研究(The Japanese Journal of Semiotic Studies)』です。これには学会発足当初の理念に返り、会則にも記された会員資格(記号、記号現象、記号体系を専門に研究する者および関連諸領域に関心をもつ者)を示す狙いがあります。SemiologyもSemioticsも広く包摂し、旧来の理論に止まらない射程を表したい、と。
実は、新しく入会された方から「…記号学については勉強不足で…」という声をお聞きすることが増えていました。その度に私たちは「記号学/論」という看板の窮屈さとともに、「果たして我々の関心を基礎づける理論はアップデートされてきたのか」と自問を繰り返してきました。敢えてSemiotic Studiesの名を掲げる意味はそこにあります。
より投稿いただきやすい形式と発信方法を整え、皆さんの研究を数多く寄せていただき、そのコンスタントな積み重ねによって知的循環を創出したい――大会の企画や学会誌と切り離し、自由にさまざまな領域に記号現象を見出し、新しい理論を形づくっていく冒険の場として、この電子ジャーナルを位置づけていけたらと考えています。
デジタル技術の浸透やサステナビリティを問う新たな認識環境の中で、「記号の学」自体も大きく変化しています。今年はこのジャーナルの発行を皮切りに、大会の在り方も見直し、大会以外の研究事業も活性化させていきたいと思います。別紙に記載しましたようにご意見や叱咤など、忌憚なくお寄せいただけますよう、お願いいたします。
水島 久光 (東海大学)